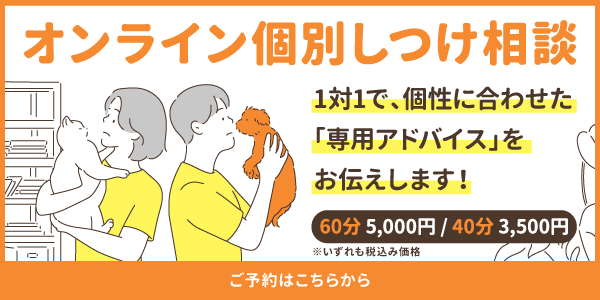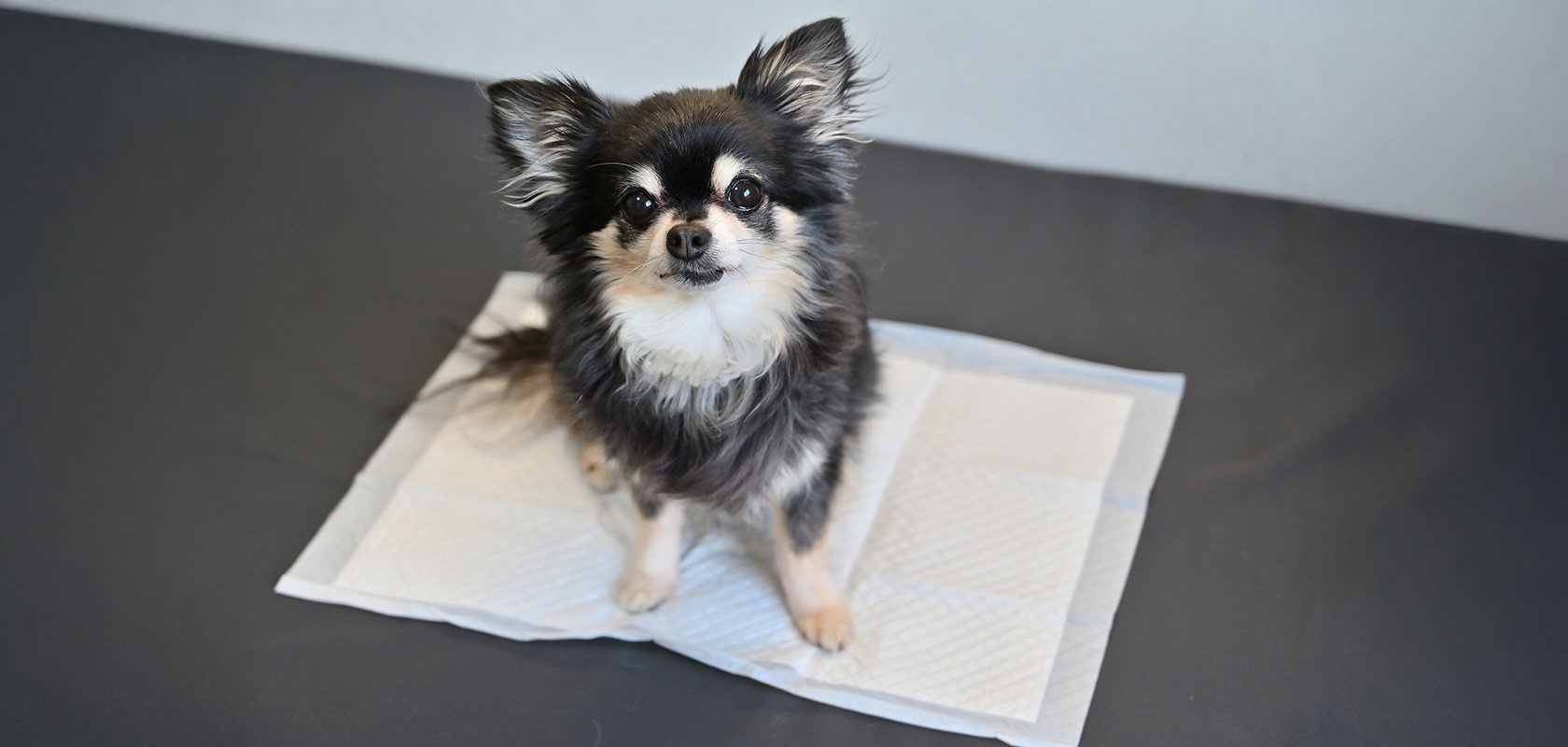子犬の噛み癖がひどい場合のしつけ方や予防方法を解説

「子犬の噛み癖はしつけで直る?」
「噛み癖を直す方法は?」
「噛み癖がひどいのはなぜ?」
子犬のしつけについて、このような疑問があるのではないでしょうか。噛み癖を直すには、噛んだら遊びを中断してその場を離れ、1〜2分後に子犬のいる場所に戻るのがポイントです。
この記事では、子犬の噛み癖を直すポイントや原因について解説します。また、子犬の噛み癖を予防する方法についても触れています。
この記事を読めば噛み癖の原因を理解でき、正しい対処法がわかるでしょう。ぜひ最後までお読みください。
目次
- 子犬の噛み癖を放置しているとどうなる?
- 噛み癖のある子犬のしつけ方
- 子犬が飼い主を噛む主な理由6つ
- 子犬の噛み癖の予防方法
- 子犬の噛み癖やしつけに関するよくある質問
- 子犬の噛み癖は早い時期からしつけよう
子犬の噛み癖を放置しているとどうなる?

甘噛みを放置するとエスカレートし、人に対して強く噛む「本気噛み」に発展する可能性があります。本気噛みは飼い主や家族だけでなく、散歩中に出会う他の人やワンちゃんにケガをさせる事故につながる恐れがあります。
そもそも子犬が物を噛むのは、周囲の物の確認や、遊びの一環などのごく自然な習性です。しかし、この行動を「子犬だから」とそのままにすると、成犬になっても噛み癖が残る場合があります。
子犬のうちから「人の手を噛んではいけない」と根気強く教え、早期にしつけることが大切です。
噛み癖のある子犬のしつけ方

子犬の噛み癖には効果的な直し方があります。以下4つのポイントを意識してしつけを行いましょう。
- ダメなことを伝えるときの言葉を家族で決める
- 低い声と毅然とした態度で伝え、手を噛めない場所まで上げる
- ポイント2を3回まで繰り返す(3回ルール)
- 4回目に噛んできてしまった時は一度サークルに入れる
ここからは、それぞれのポイントをご紹介します。
ポイント1. ダメなことを伝えるときの言葉を家族で決める
子犬にダメなことを伝えるときの言葉を、家族で統一しましょう。「ダメ」や「痛い」など、短く分かりやすい言葉を選ぶのがポイントです。
家族がそれぞれ違う言葉で伝えると、子犬は何を基準に行動すれば良いのかわからず混乱します。家族全員が同じ言葉を使うと、一貫性のあるメッセージとして伝わり、子犬もいけない行動であることを理解しやすくなります。
ポイント2. 低い声と毅然とした態度で伝え、手を噛めない場所まで上げる
ダメと伝える際は、高い声や感情的な声は避け、低く落ち着いた声と毅然とした態度で伝えることが大切です。甲高い声で伝えると、子犬は飼い主が遊んでくれていると勘違いする場合があります。
あくまでも冷静に、短い言葉で「いけないことだ」という意思をはっきりと示しましょう。
ポイント3. ポイント2を3回まで繰り返す(3回ルール)
子犬が手を噛んだらポイント1で決めた言葉で伝えた後、すぐに遊びを中断し、手を噛めない場所まで上げましょう。その声にびっくりして噛むのを止めたら「良い子」と軽く褒めてあげてください。褒めることで「どれが正解の行動なのか」も合わせて教えていきます。
1回で覚えられない可能性もあるので、ポイント1〜2までを3回ほど繰り返すことがポイントです。
ポイント4. 4回目に噛んできてしまった時は一度サークルに入れる
もし、4回目に噛んできてしまった際は一度サークルに入れて、「噛んだら楽しい時間はおしまいだよ」と教えてあげましょう。愛犬がサークルの中で反省し、「どうして楽しい時間が終わってしまったんだろう?」と考える時間を与えてあげます。
この場合、トイレトレーニングと組み合わせ、次にサークルから出すタイミングは「トイレが成功した時」がベストです。
子犬が飼い主を噛む主な理由6つ

子犬が飼い主を噛むときには何らかの理由があります。効果的なしつけを行うには、以下6つの理由を理解しましょう。
- 好奇心で口に入れて確かめている
- 遊びや興奮でじゃれている
- 飼い主の気を引こうとしている
- ストレスや欲求不満を感じている
- 歯の生え変わりで不快感がある
- 不安や恐怖から抵抗している
ここでは、子犬が飼い主を噛む理由とそれぞれに対応する予防策を紹介します。
理由1. 好奇心で口に入れて確かめている
子犬は好奇心から身の回りの物を噛んで、それが何かを学習します。人間の赤ちゃんが何でも口に入れて確かめるのと同じように、成長過程では自然に見られます。
この場合、噛んではいけない物を学習させる方法が有効です。声かけやご褒美ではうまく学習できないときは、「予防方法4. しつけ用のスプレーを使用してみる」という方法もあります。
理由2. 遊びや興奮でじゃれている
遊びが盛り上がって興奮のあまり、じゃれるつもりで飼い主の手を噛むことがあります。この場合、子犬は悪気なく「人間の手=動くおもちゃ」と認識している可能性があります。
このタイプは、噛んでも良い対象と悪い対象を教えることが重要です。詳しくは「予防方法1. 噛んで良いおもちゃを与える」でも解説しています。
理由3. 飼い主の気を引こうとしている
「もっと遊んでほしい」「自分に注目してほしい」と伝えるために、飼い主を噛むことがあります。特に、飼い主がスマートフォンを見ていたり、テレビに集中していたりするときに、気を引こうとして噛む行動が見られがちです。
このような要求による噛み癖には、子犬との関わり方にメリハリをつけることが効果的です。詳しくは「予防方法2. 一緒に遊ぶ時間を明確にする」でも解説しています。
理由4. ストレスや欲求不満を感じている
ストレスや欲求不満があると、噛むことで発散させるケースがあります。例えば運動不足や飼い主とのコミュニケーション不足、生活環境の変化などが原因です。
ストレスが原因と考えられる場合は、適切な方法でエネルギーを発散させることが大切です。詳しくは「予防方法3. 散歩や遊びで運動不足を解消する」でも解説しています。
理由5. 歯の生え変わりで不快感がある
生後4カ月から6カ月頃の子犬は歯茎がむずがゆく、その不快感を和らげようとして、手近な物を噛みます。歯茎がむずがゆいのは、乳歯から永久歯へと歯が生え変わる時期だからです。
歯の生え変わりによるむずかゆさが原因の場合は、欲求を満たし不快感を軽減することが助けになります。詳しくは「予防方法1. 噛むおもちゃを与える」でも説明しています。
理由6. 不安や恐怖から抵抗している
大きな音に驚いたり、知らない人や場所に恐怖を感じたりしたときに、自分を守ろうとして噛みつくことがあります。例えば、ブラッシングや爪切りなどのお手入れ中に、嫌なことをされそうだと感じて抵抗のために噛んでしまうケースです。
不安や恐怖心が原因の場合は、さまざまな刺激に慣れさせ、安心感を与える社会化トレーニングが必要です。詳しくは「予防方法5. 社会化トレーニングで環境に慣れてもらう」でも解説します。
子犬の噛み癖の予防方法

噛み癖がついてから直すだけでなく、以下5つのような予防方法も有効です。
- 噛んで良いおもちゃを与える
- 一緒に遊ぶ時間を明確にする
- 散歩や遊びで運動不足を解消する
- しつけ用のスプレーを使用してみる
- 社会化トレーニングで環境に慣れてもらう
ここでは、子犬の噛み癖を予防する方法を紹介します。
予防方法1. 噛んで良いおもちゃを与える
人の手や家具の代わりに、噛んでも良い専用のおもちゃを与えて欲求を満たしてあげましょう。子犬には「噛みたい」という本能的な欲求があり、おもちゃを与えることで噛んで良い物とそうでない物の区別が付きやすくなります。
代表的なのは、ロープやゴムボール、骨型のおもちゃです。さまざまな種類のおもちゃを用意し、愛犬の好みに合わせて選んであげると良いでしょう。
予防方法2. 一緒に遊ぶ時間を明確にする
サークルから出ている間は飼い主と一緒に遊ぶ時間にして、明確なルールを決めましょう。サークルから出して常に自由にさせていると、子犬は「いつでも遊んでもらえる」と期待します。その結果、飼い主の気を引くために噛むことがあります。
トイレを完全に覚えるまでは、トイレトレーニングのご褒美で遊ぶ時間以外、サークルの中で自立心を養う時間にしましょう。その分、遊ぶ時間ではしっかり飼い主が愛犬と向き合って、おもちゃを使って遊び、ワンちゃんの気持ちを発散させてあげることが大切です。
予防方法3. 散歩や遊びを取り入れて運動不足を解消する
運動でエネルギーを十分に発散させてあげると、ストレスによる噛み癖の予防や軽減につながります。日々の散歩では足りないときは、室内でもボール遊びや引っ張り合いなどの遊びを取り入れて運動量を増やしましょう。
体を動かすと、ストレス解消だけでなく、心身の健康維持にもつながります。
予防方法4. しつけ用のスプレーを使用してみる
これまで紹介したしつけや予防方法を試しても噛み癖が直らない場合は、噛み癖防止用のスプレーを試すのも1つの方法です。
噛み癖防止用のスプレーは、子犬が嫌がる苦い味などがする液体です。健康に害はなく、噛まれたくない家具に塗布すると「これを噛むと嫌な味がする」と学習させられます。
予防方法5. 社会化トレーニングで環境に慣れてもらう
恐怖や不安が原因で噛み癖がある子犬には、さまざまな人や物、音、状況に慣れさせる「社会化トレーニング」が必要です。
例えば、ブラッシングを怖がるのであれば、まずはブラシを見せることから始めましょう。次にブラシで体に優しく触れる、というように段階を踏んで慣れさせます。
焦らず少しずつ経験を積ませることで、愛犬の自信を育み、恐怖心からの噛み癖を減らせます。
子犬の噛み癖やしつけに関するよくある質問
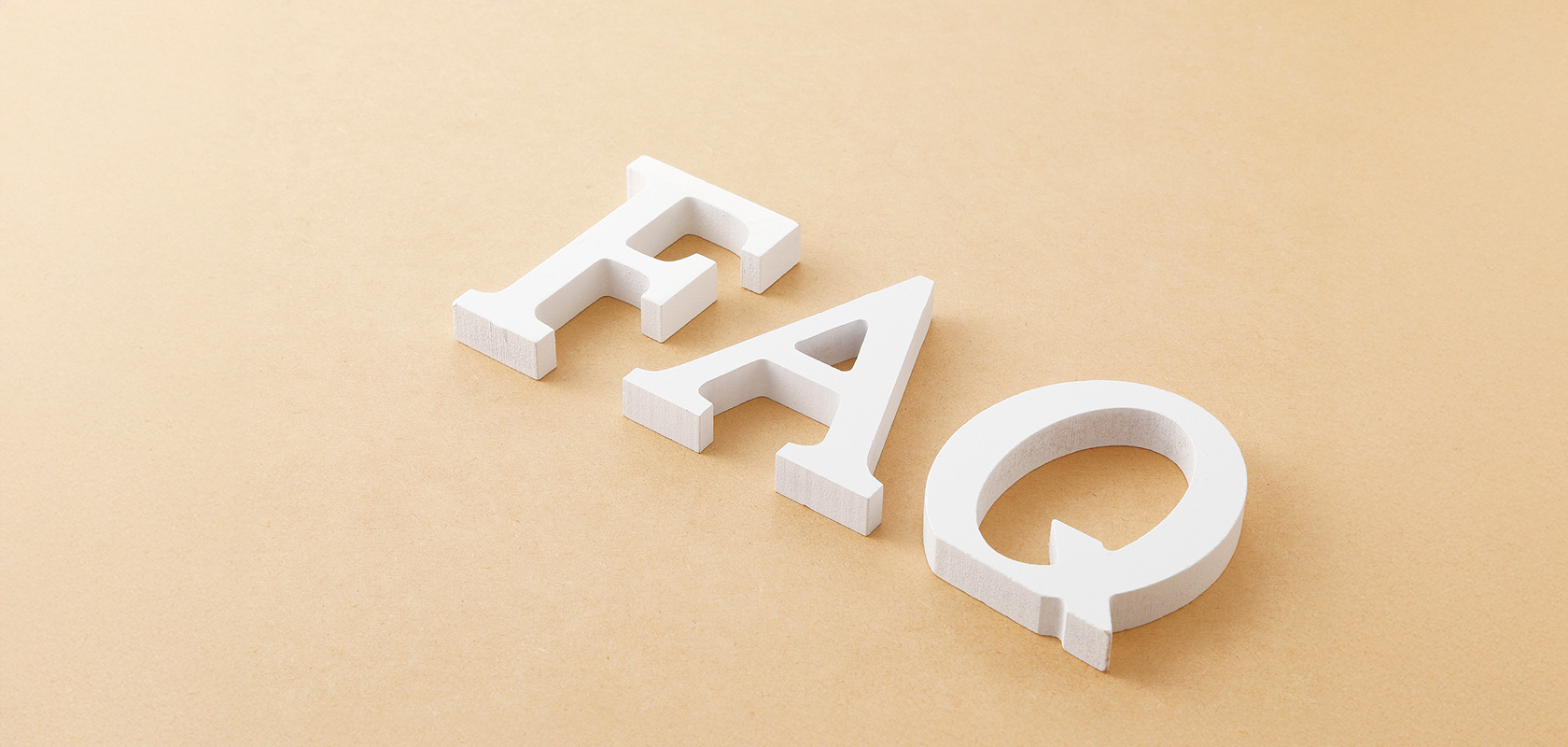
最後に、子犬の噛み癖やしつけに関してよくある質問をまとめました。
子犬の噛み癖は成長とともに自然に直る?
子犬の甘噛みは成長過程で見られる自然な行動ですが、何もしなくても必ず直るとは限りません。噛む力の加減を学ぶ機会がないまま成犬になると、より深刻な問題に発展しかねません。
子犬のうちから根気強くしつけを続け、トラブルに発展するのを防ぎましょう。
家族で噛む人と噛まない人がいるのは?
愛犬が家族の中で特定の人だけを噛む場合、いくつかの理由が考えられます。
1つ目は、その人との関係性の中で、自分の方が優位だと感じているケースです。要求をすぐ聞いてくれる人や、曖昧な態度をとる人に対して、自己主張として噛むことがあります。
2つ目は、その人に対して恐怖やストレスを感じているケースです。例えば食事中やくつろいでいるとき、無理に触ると不安を感じて防衛的に噛むことがあります。
家族全員が一貫した態度で接し、愛犬のプライベートな空間を尊重することが大切です。
子犬の噛み癖がひどいときはどうしたらいい?
噛んだときに血が出るほど噛み癖がひどく、家庭での対応が難しいと感じる場合は、専門家への相談をおすすめします。
ドッグトレーナーによるしつけ教室に参加すれば、専門的な知識と技術に基づいた、その子に合った効果的なしつけ方法を学べます。プロの助けを借りることは、問題解決への近道です。
子犬の噛み癖は早い時期からしつけよう

噛む行動は子犬にとっては自然な習性の一部ですが、放置すると本気噛みなどの深刻な問題に発展する可能性があります。
まずは、「ダメ」や「痛い」など、短く分かりやすい言葉でダメなときの伝え方を決めましょう。ダメなことを伝える際は、低い声と毅然とした態度で伝えて手を噛めない場所まで上げる、それを3回ほど繰り返し、噛むのを止めたら「良い子」と軽く褒めてあげましょう。4回目で噛んだ場合は一度サークルに入れて「どうして楽しい時間が終わってしまったんだろう?」と考える時間を与えてあげてください。
もし、家庭での解決が難しいときは、専門家の力を借りてみましょう。早い段階から適切な対応をすると、習慣として定着しにくくなります。愛犬の噛み癖が気になっている方は、ぜひこの記事で紹介したポイントを参考にしてみてください。
ドッグトレーナーのコメント
 「甘噛みだからいつかなくなると思っていた」というお声もたくさんいただきますが、いつかなくなるものではありません。
「甘噛みだからいつかなくなると思っていた」というお声もたくさんいただきますが、いつかなくなるものではありません。そんな時は、ドッグトレーナーなどの専門家に相談し、正しい方法を学ぶことが、ワンちゃんとの暮らしを安心して楽しむための第一歩になります。
オンライン個別しつけ相談のご案内
ペッツファーストでは、個別にオンラインでしつけ相談(有料)を承っております。しつけのお悩みから、解決方法のレクチャーまで、じっくり相談されたい方のために、時間は1回最大60分。ワンちゃん、ネコちゃんのしつけでお困りの方は下記よりご予約ください。