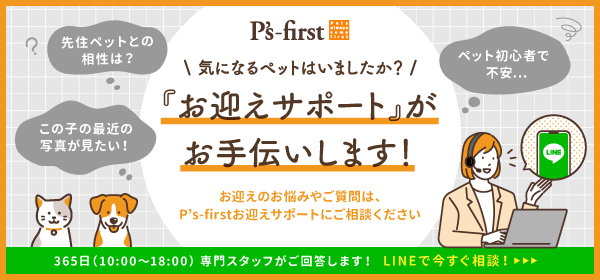【初心者向け】初めての愛犬の飼い方!事前準備や飼い始め1週間の過ごし方も解説

「ワンちゃんの飼い方は?」
「室内飼いする場合のレイアウトは?」
「室内犬の場合ケージに入れっぱなしでも大丈夫?」
初めてワンちゃんをお迎えする方には、このような疑問があるのではないでしょうか。ワンちゃんを飼い始めるときは、飼育環境を整えたり必要なアイテムを揃えたりなどの準備が必要です。
この記事では、初心者が知っておきたい愛犬の飼い方について紹介します。事前準備に加え、お迎え後の食事やお手入れ、トレーニングについても触れていきます。
この記事を読むことで初心者の方でも愛犬の飼い方がわかり、お迎えまでに必要な準備や段取りがわかるでしょう。ぜひ参考にしてください。
目次
- 【飼育環境編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 【食事編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 【お手入れ編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 【トレーニング編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 【予防接種編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 【散歩編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
- 愛犬の飼い始め一週間の過ごし方
- 愛犬の飼い方に関するよくある質問
- 愛犬の飼い方を知ってワンちゃんを迎える体制を整えよう!
【飼育環境編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方

ワンちゃんが安心して暮らせる飼育環境を整えられるよう、以下の4つを済ませておきましょう。
- 必要なアイテムを準備する
- 危険なものを排除する
- レイアウトを整える
- マイクロチップ情報を登録する
初めてお迎えする方でも、これらのポイントを押さえておけば心配ありません。ここでは、飼い始める前に準備しておきたいアイテムや、安全な住環境を整えるためのポイントをご紹介します。
1.必要なアイテムを準備する
| 項目 | アイテム |
|---|---|
| 必須アイテム |
|
| できれば準備したいもの |
|
ワンちゃんをお迎えする前に、必要なアイテムを揃えましょう。
ケージやベッド、トイレ・トイレシートは生活の基本となる必須アイテムで、ワンちゃんの大きさに合わせて選びます。食器はフード用とお水用に2つ必要です。フードについては「1. 愛犬に適したフードを準備する」で詳しく解説しています。
ワンちゃんには適度な運動が必要であるため、遊びや散歩に備えておもちゃやカラー、リードなども忘れずに準備しましょう。
余裕がある場合は、洋服やブラッシング用品、空気清浄機なども用意するとより快適な飼育環境が整います。
2.危険なものを排除する
| 項目 | 例 | 対策 |
|---|---|---|
| 危険なもの |
|
|
| 誤飲・誤食の可能性があるもの |
|
|
| 食べてはいけないもの |
|
|
愛犬にとって安全な環境にするため、室内にある危険なものはあらかじめ取り除きましょう。特に、電気コードや暖房器具は感電や火災の恐れがあります。カバーをかぶせたり、手が届かない場所に配置しましょう。
ゴミ箱や小物入れにある医薬品、電池、洗剤、ティッシュなどは誤飲・誤食の危険性があります。ゴミ箱には蓋をつける、鍵つきの棚に収納するなどの対策が必要です。
チョコレートやネギ類など、人が日常的に食べるものでもワンちゃんにとっては毒になります。間違って食べてしまわないよう手の届かない場所に保管したり、キッチンに柵を設置したりしましょう。
3.レイアウトを整える
愛犬が安心して過ごせるように、室内のレイアウトを整える必要があります。まずは、サークルやケージで愛犬専用のスペースを確保し、その中にトイレやベッドを設置しましょう。ケージは、静かで落ち着ける場所に配置するのがポイントです。
フローリングはワンちゃんの足が滑りやすく、転倒する可能性があります。滑り止め効果のあるカーペットやペット用マットを敷くと安心です。
キッチンや階段など危険な場所には、ペットゲートや柵を使って侵入できないようにしておきましょう。
4.マイクロチップ情報を登録する
愛犬を迎えたら、マイクロチップ情報の登録が必須です。動物愛護管理法により、ワンちゃんへのマイクロチップ装着と情報登録が義務化されています。
登録は「犬と猫のマイクロチップ情報登録」からオンラインで可能です。災害や迷子などの際、保護されたワンちゃんが飼い主のもとに戻る手がかりになるため、できるだけ早くおこないましょう。
【食事編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方

愛犬の食事は、以下の3つのようにおこないましょう。
- 愛犬に適したフードを準備する
- ワンちゃんが食べられない食材を把握する
- 適正量を適正回数与える
食事は健康維持に欠かせない重要な要素で、適切なフード選びや食事の管理が必要です。ここでは、愛犬に合ったフードの選び方や食材の注意点、食事の回数や量について解説します。
1.愛犬に適したフードを準備する
ワンちゃん用のフードを準備する際は、以下の3つのポイントがあります。
- フードは総合栄養食を選ぶ
- ライフステージに合わせて選ぶ
- 愛犬のサイズに合わせて選ぶ
前提として、フードは総合栄養食を選ぶことが推奨されます。総合栄養食なら必要な栄養素をバランスよく摂取でき、健康を保てます。
次に、ライフステージに合わせたものを選びましょうたとえば子犬には子犬用のフードを、成犬には成犬用のものを選びます。
愛犬のサイズに合わせてフードを選ぶのもポイントです。ワンちゃんのサイズによって栄養素や最適な粒の大きさが異なるためです。小型犬には小型犬用、中型犬には中型犬用のものを準備します。
2.ワンちゃんが食べられない食材を把握する
愛犬の安全を確保するために、食べられない食材を把握することが重要です。たとえば以下のような食べ物は、ワンちゃんに与えてはいけません。
- 生魚
- 塩味の強いもの
- チョコレート
- キシリトール
- ブドウ
- フライドチキンなど鶏の骨
- 生卵白
- ネギ類
- イカやタコ
- 人間用牛乳
- 1日1回歯磨きする
- 1日1回ブラッシングする
- 月に1回必要なお手入れをする
- 口の周りを触る練習をする
- 歯磨きシートで歯をなでる練習をする
- 歯ブラシで歯を磨く
- 体を触られることに慣れさせる
- ブラシを見慣れさせる
- リラックスできる体勢にする
- ブラシを体に当てて慣れさせる
- 嫌がらない場所からブラッシングする
- 全体をコームで整える
- 毛玉をほぐす
- シャンプー
- 爪切り
- 耳掃除
- 肛門腺絞り
- 肉球(足の裏)ケア
- スキンシップを取る
- 名前を教える
- アイコンタクトを教える
- トイレを教える
- 社会化をおこなう
- あごの下
- 腰付近
- 耳のつけ根(裏)
- 首(肩部分)
- おなか
- 脇の下
- 愛犬の排泄サインやタイミングを知る
- 排泄サインがあったらトイレに連れていく
- 成功したら褒める
- トイレのコマンドを教える
- 室内環境に慣れさせる
- 人に慣れさせる
- 体に触れるものに慣れさせる
- 外に慣れさせる
- 狂犬病予防注射を受ける
- 混合ワクチン接種を受ける
- フィラリア予防をおこなう
- 散歩で身に着けるものに慣れさせる
- 抱っこ散歩で外に慣れさせる
- 家の中で歩き方を教える
- 短い散歩から始める
- 自分の場所を教える
- トイレを促す
- フードをあげる
- コミュニケーションを取る
- 室内環境に慣れてもらう
- トイレトレーニングを始める
- 愛犬を飼うとできなくなることは?
- 愛犬を飼うのに向いている人の特徴は?
- 室内犬はケージに入れっぱなしでもOK?
- 長期間の外出
- 旅行
- エアコンの節約
- 時間の確保
- 生き物が好き
- 責任感がある
- 変化に対応できる
- 生活に余裕がある
これらの食材は絶対に避け、誤飲や誤食がないように注意しましょう。
3.適正量を適正回数与える
愛犬には適切な量と回数で食事を与えることが大切です。フードのパッケージに記載されたガイドラインを参考に、ワンちゃんの体重や年齢に応じた適正量を計算しましょう。
与えすぎると肥満になるリスクがあり、逆に少なすぎると栄養不足につながることもあります。特に成長期の子犬は、必要なカロリーや栄養素が異なるため、ライフステージに合わせた食事管理が必要です。
【お手入れ編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方

愛犬の健康を保つためのお手入れは、以下の3つのようにおこないましょう。
初めは難しく感じるかもしれませんが、少しずつ慣れていけば大丈夫です。ここからは、それぞれのお手入れについて解説します。
1.1日1回歯磨きする
愛犬の健康のために、1日1回の歯磨きを習慣にしましょう。ワンちゃんは歯垢が溜まりやすく、放っておくと数日で歯石になり、歯周病の原因になります。
最初から歯ブラシで歯磨きできる子は少ないため、愛犬の様子を見ながら以下の3つのステップで慣らしていきましょう。
子犬の頃から歯磨きをしていると、早く慣れてくれます。
2.1日1回ブラッシングする
ブラッシングは、愛犬の健康と美容を保つために1日1回は必要なケアです。被毛が絡まったままだと汚れが溜まり、皮膚トラブルの原因になります。抜け毛の多い犬種は、特にこまめなケアが必要です。
歯磨きと同じで、ブラッシングも初めからできる子は少ないため、次のようなことを心がけながら少しずつ慣らしましょう。
まずは体を触られることに慣れさせ、ブラシを見せて匂いを嗅がせるなどして、少しずつ慣らしましょう。
ブラッシングは、次のような3つの手順でおこないます。
ブラッシングは、リラックスできる体勢で、背中など嫌がりにくい部位から始めるのがポイントです。毛玉やもつれは無理に引っ張らず、スリッカーブラシやコームを使い分けて丁寧に整えていきます。
3.月に1回必要なお手入れをする
月に1回必要なお手入れは、以下の通りです。
ワンちゃんによっては、シャンプーや爪切り、耳掃除を嫌がる子もいます。また、肛門腺がどこにあるのかわからず、肛門腺絞りが難しいと感じる方もいるでしょう。これらのお手入れは、トリミングサロンでもできるため、無理せずプロにお願いしましょう。
【トレーニング編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方

ワンちゃんをお迎えしてから必要なしつけやトレーニングは、以下の5つの通りです。
できるだけ早くトレーニングをおこなうことで、愛犬との信頼関係を築き、快適に過ごせます。ここでは、それぞれのトレーニングについて解説します。
1.スキンシップを取る
愛犬との信頼関係を築く第一歩は、日常的なスキンシップです。優しく体をなでることで、飼い主が安心できる存在であることをワンちゃんに伝えられます。
ワンちゃんがなでられて嬉しいのは、以下のような場所です。
ただし、ワンちゃんによってはこれらの場所でも嫌がることがあります。愛犬の様子を見ながらなでてあげましょう。
愛犬とスキンシップを取る際のポイントは、リラックスしているタイミングになでることです。激しくなでると痛がる場合もあるため、ゆっくりと優しくなでてあげましょう。
体をなでると異常に気づくこともあり、健康チェックにもなります。本格的なトレーニングを始める前に、まずはスキンシップで絆を強めましょう。
2.名前を教える
愛犬が自分の名前を覚えると、しつけや日常のコミュニケーションがスムーズになります。名前を呼んでこちらに注目したタイミングで、おやつを与えてたくさん褒めてあげましょう。この繰り返しによって、名前が「よいことが起きるサイン」として愛犬にインプットされます。
なお、名前を呼ぶときに叱るのは避けましょう。名前がネガティブな体験と結びつくと、ワンちゃんは名前を覚えたがらなくなるからです。スキンシップを取って信頼関係を深めながら、遊びの中で自然に名前を覚えてもらいましょう。
名前を覚えれば、今後のトレーニングや外出先でも呼び戻しができるため、安全面でも役立ちます。
3.アイコンタクトを教える
アイコンタクトとは、愛犬が飼い主の目を見て意識を集中させるトレーニングです。しつけや散歩中の指示を伝える際に、飼い主に注目する習慣があるとスムーズにコミュニケーションが取れます。
練習方法としては、まずおもちゃやおやつを愛犬の前に見せて興味を引き、その後、飼い主の顔の近くに移動させます。目が合った瞬間に名前を呼んで褒め、おやつや遊びでご褒美を与えましょう。
これを繰り返すことで、「目を合わせる=よいことがある」と認識させられます。アイコンタクトができるようになると、今後のトレーニングもスムーズに進みやすくなります。
4.トイレを教える
トイレトレーニングは、愛犬を迎えたらすぐ始めるのが理想です。早く覚えてもらうと、飼い主の負担が軽減します。
トレーニング方法は、以下の4つの手順の通りです。
まずは排泄のサインやタイミングを把握することが重要です。そわそわする、床の匂いを嗅ぐ、ぐるぐる回るなどの行動が見られたら、すぐにトイレに連れていきましょう。
成功したら、すぐにしっかり褒めてあげることで「ここで排泄するとよいことがある」と学習します。慣れてきたら、「ワンツー」などのコマンドを使い、合図で排泄できるように教えると外出時にも便利です。
失敗しても叱らず、成功体験を積ませてあげることがトレーニング成功のポイントです。失敗するたびに叱ると排泄が悪いことだと認識する可能性があり、身につきません。ワンちゃんが失敗しても飼い主は淡々と掃除し、焦らず根気よく続けましょう。
5.社会化をおこなう
愛犬が人間社会で安心して過ごせるようにするには、社会化がとても大切です。社会化が不十分だと、散歩や通院時に怯えたり、他人やほかのワンちゃんに対して攻撃的になったりすることもあります。こうした問題行動を防ぐためにも、できるだけ早い段階から社会化を始めましょう。
社会化をおこなう際は、以下の4つのステップで徐々に慣れてもらうことがポイントです。
まずは室内の環境や音に慣れさせ、さまざまな人と接する機会を作ります。家族や友人はもちろん、子犬のうちから動物病院のスタッフと触れ合うことで、病院にも慣れやすくなります。
カラーやリード、ブラシなどの体に触れるものに慣れることも大切です。これらのアイテムに慣れることで、トレーニングやお手入れがしやすくなります。
外の世界には見慣れない音や景色がたくさんあります。最初は抱っこやカートで外に連れ出し、無理のない範囲で経験を重ねていきましょう。
【予防接種編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方
愛犬の健康を守るためには、以下のような予防接種が欠かせません。
予防接種を受けることで病気のリスクを減らし、元気で長生きできる環境を整えられます。ここでは、基本的な予防接種について解説します。
1.狂犬病予防注射を受ける
狂犬病予防注射は、愛犬の健康を守るために欠かせない予防措置です。狂犬病は人間にも感染する病気ですが、日本国内では発生していません。しかし、海外から持ち込まれる可能性があるため、すべてのワンちゃんに予防接種が義務づけられています。
狂犬病予防注射のスケジュールは、お迎えしたときのワンちゃんの月齢に応じて異なります。具体的なスケジュールは、以下の通りです。
| ワンちゃんの月齢 | スケジュール |
|---|---|
| 生後90日以内 | 生後90日を経過した日から30日以内 |
| 生後91日以降 | お迎え日から30日以内 |
予防注射が終わったら、動物病院から証明書(狂犬病予防注射済証)を貰って近くの役所などに持参し、狂犬病予防注射済票を交付してもらいましょう。自治体のホームページなどを事前に確認しておくと安心です。
また、注射済票はドッグラン、ペットホテル、トリミングサロンなどを利用する際に必要なことがあります。そのため、無くさないよう注意しましょう。
2.混合ワクチン接種を受ける
混合ワクチンとは、ワンちゃんがかかりやすい複数の病気を予防するものです。義務ではありませんが国内で発生しているワンちゃんの病気を予防するものでもあります。接種しておくと安心です。
また、お迎えするワンちゃんが子犬か成犬かによって、以下のようにスケジュールが異なることも覚えておきましょう。
| ワンちゃん | スケジュール |
|---|---|
| 子犬 | 1年に3回* |
| 成犬 | 1年に1回(初めてなら1年に2回) |
*摂取時の月齢やワクチンの種類によって変動があります
なお、外に出ないワンちゃんでも飼い主によって病気が持ち込まれることがあるため、ワクチン接種は備えになります。定期的にワクチンを受けることで、愛犬を重大な病気から守り、健康を維持できます。
3.フィラリア予防をおこなう
フィラリアは、蚊を媒介にしてワンちゃんに感染する寄生虫病です。心臓や肺の血管に寄生し、最終的には命に関わることもあるため、予防して対策することが重要です。
予防は春から秋にかけて行うことが一般的ですが、最近では暖房設備の発達などにより一年中予防を行う必要がある場合もあります。
予防薬については、獣医師に相談するとよいでしょう。
【散歩編】初心者が知っておきたい愛犬の飼い方

愛犬の散歩は、以下の4つのステップで始めましょう。
ここからは、それぞれの方法について解説します。
1.散歩で身に着けるものに慣れさせる
散歩デビューの前に、まずはカラーやハーネス、リードなど散歩時に必要なアイテムに慣れてもらいましょう。これらのアイテムはワンちゃんにとって初めての感覚なので、いきなり装着すると驚いて嫌がることがあります。
まずは部屋の中で匂いを嗅がせるなどして存在に慣れさせ、警戒心が薄れてきたら短時間だけカラーやハーネスを装着してみます。その際、おやつを与えながらおこなうとポジティブなイメージがつきやすいためおすすめです。
ワクチン接種前は実際に外を歩くことはできませんが、お散歩アイテムに慣れる練習はできます。積極的にトレーニングをおこないましょう。
2.抱っこ散歩で外に慣れさせる
いきなり散歩に連れていくのではなく、「抱っこ散歩」からはじめるのがおすすめです。抱っこ散歩とは名前の通り飼い主がワンちゃんを抱っこして移動する散歩のことです。
多くのワンちゃんは、初めての外の世界に驚いたり怖がったりします。そこで、スリングやキャリーバッグに入れて外を歩くことで、安心しながら経験できます。外の空気や音、匂い、人の動きなどたくさんの刺激を感じることで、徐々に警戒心を解いていけるでしょう。
3.家の中で歩き方を教える
本格的な散歩を始める前に、まずは家の中でリードやカラーをつけて歩く練習をしましょう。
慣れないうちはリードを嫌がったり、歩かずに座り込んでしまう子もいます。この場合は無理に引っ張らず、少しでも前に進んだらおやつや優しい声かけでたくさん褒めてあげましょう。
4.短い散歩から始める
ワクチン接種を終えたら、短い距離からスタートしましょう。まずは短時間、少ない距離を歩いてみて、愛犬の反応を見ながら距離を延ばしていきます。
ワンちゃんが歩かない場合、恐怖や不安が原因かもしれません。その際は、抱っこ散歩などを取り入れて徐々に慣らしていきましょう。
犬種や年齢、体調によって適切な散歩時間や距離は異なるので、愛犬に合ったペースで進めることが重要です。
愛犬の飼い始め一週間の過ごし方

| 一週間の過ごし方 | やること |
|---|---|
| 初日 |
|
| 翌日以降 |
|
愛犬を迎えてからの最初の一週間は、環境に慣れさせ、信頼関係を築くための大切な時期です。
初日は愛犬に自分の場所を教え、安心してもらうことから始めましょう。新しい環境に戸惑うかもしれませんが、落ち着いてサポートしてあげることが大切です。
サークルやケージにトイレシートを用意し、排泄を促します。できたらしっかり褒めてあげましょう。
翌日以降はコミュニケーションを取ることで絆を強め、少しずつ室内での生活に慣れさせましょう。トイレトレーニングもこのタイミングでスタートし、失敗しても優しく対応することがポイントです。
無理せず、愛犬のペースで進めることを心がけ、毎日のコミュニケーションを大切にしましょう。
愛犬の飼い方に関するよくある質問

愛犬の飼い方に関するよくある質問は、以下の通りです。
あらかじめ疑問を解消することで、自信を持ってお迎えできるでしょう。ここからは、それぞれの質問に回答します。
愛犬を飼うとできなくなることは?
愛犬を飼うと、以下のようなことができなくなるといわれることがあります。
ワンちゃんは長時間留守番ができるわけではないため、長期間の外出や旅行ができなくなります。一緒にお出かけができない場合は、ペットホテルに預けるなどの対応が必要です。
また、ワンちゃんの健康面を考え、室温を一定に保つためエアコンはつけっぱなしになる期間があります。
ほかにも、日々のお世話の時間が必要になることから、ワンちゃんとの時間が優先的になるあまりに、自分の時間の確保に工夫が必要になってくることも。
ワンちゃんをお迎えすることで、このような生活の変化があることを理解しておきましょう。
愛犬を飼うのに向いている人の特徴は?
愛犬を飼うのに向いている人の特徴は、以下の通りです。
生き物が好きなことはもちろん、飼い主として責任をもってお世話ができることやワンちゃんと暮らしていくことに対応できるかどうかが大切です。
そして、一緒に生活し続けることができるぐらい生活に余裕があるかどうかもふまえて、愛犬を飼うのに向いているかを考えてみるとよいでしょう。
室内犬はケージに入れっぱなしでもOK?
室内犬をケージに入れっぱなしにするのは避けるべきです。長時間ケージに閉じ込めると、運動不足になったりストレスが溜まったりして、問題行動が起こる可能性があります。
お迎え直後で、すべてのワクチンが終わっていない場合は、少しずつケージの外で遊ばせます。ワクチンが完了したあとは、ケージから出す時間は徐々に増やしてあげましょう。
ケージはあくまでトイレトレーニングや避難場所として利用し、飼い主が見守れる時間帯はケージから出してあげることが大切です。
愛犬の飼い方を知ってワンちゃんを迎える体制を整えよう!

愛犬を迎えるときは、ワンちゃんに必要な生活環境やトレーニング、予防接種など、総合的なケアについて理解しましょう。まずは、必要なアイテムや安全な環境を整え、愛犬が快適に過ごせる場所を作ります。
食事やお手入れの習慣も大切で、成長段階に合わせて適切なフードを用意し、適量与えることがポイントです。毎日のブラッシングや歯磨きなどのケアも欠かせません。
ワンちゃんが快適に人間社会で暮らしていくには、トイレトレーニングや社会化が必要です。お迎えからすぐに進め、愛犬が安心して新しい生活に馴染めるよう配慮しましょう。
また、スキンシップや遊びを通じて信頼関係を築くことも重要です。愛犬との関係を深め、生活をより豊かなものにしていきましょう。